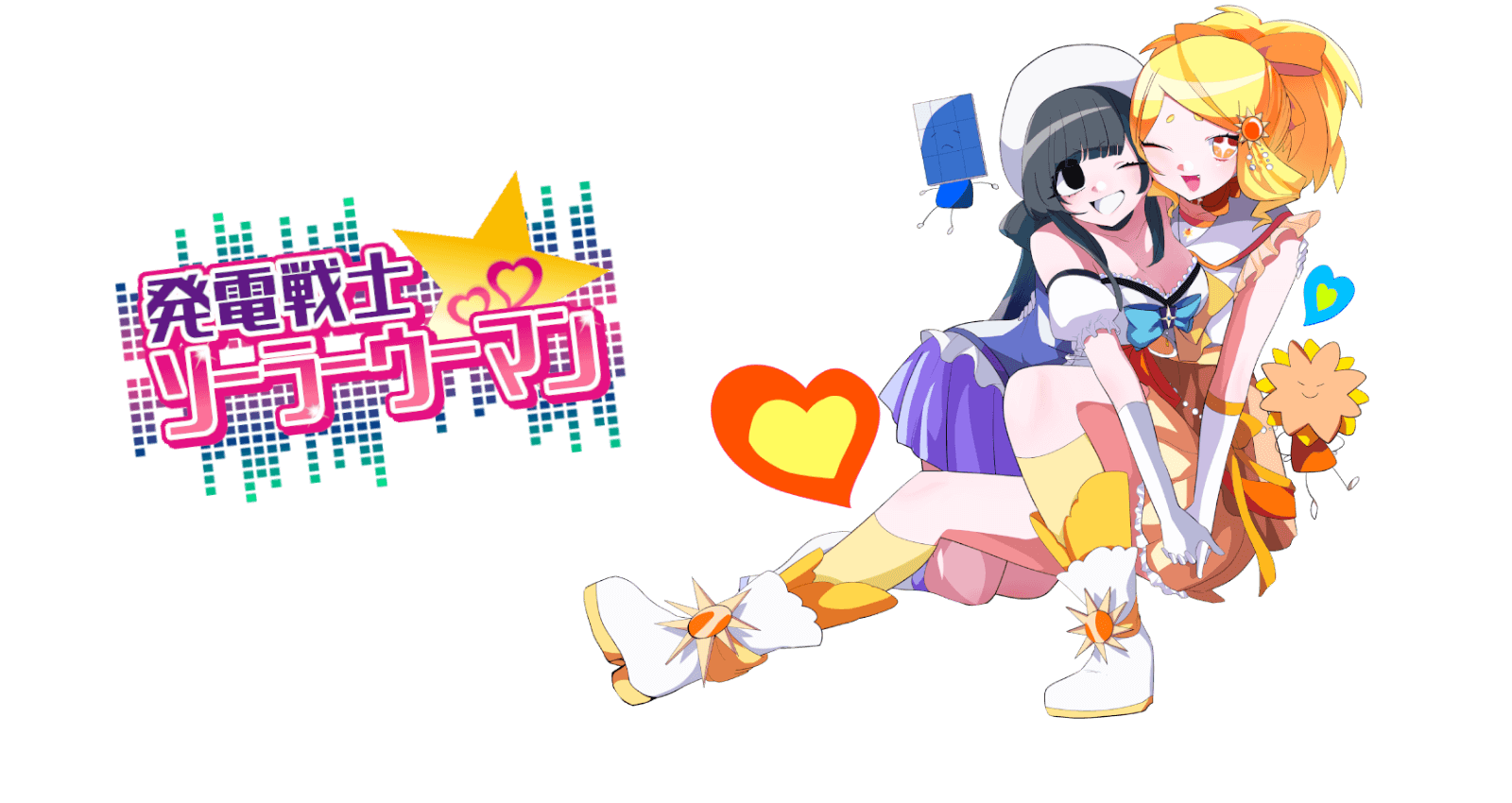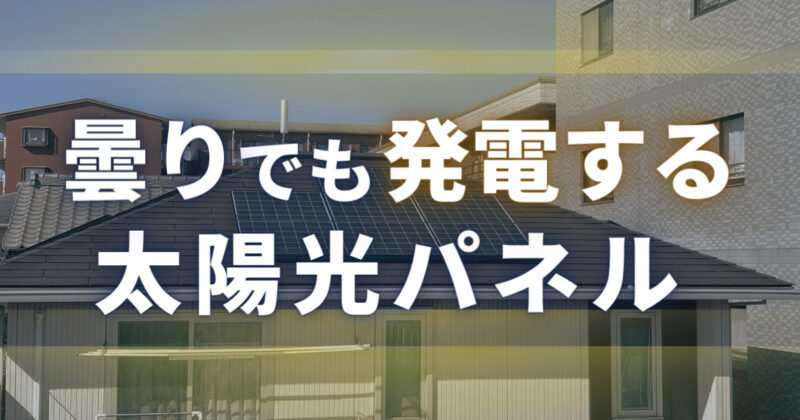晴れた日ばかりではない気候の中で、太陽光発電の利回り向上を考えると、やはり曇りの日でも効率的に発電できる太陽光パネルへ注目が集まります。
本記事では、そんな曇りでも発電する太陽光パネル厳選TOP4をご紹介します。
曇りの日にも力を発揮する太陽光パネルは、いったいどのメーカーの太陽光パネルなのでしょうか?
曇りでも発電する太陽光パネル厳選TOP4

ソーラーパネル導入を検討する第一歩として、太陽電池パネルの性能や特徴を知ることが大事ですが、そもそも発電効率の良い太陽パネルを販売しているのはメーカーはあるのでしょうか?
本章では、国内外の老舗4社の太陽光パネルについてまとめてみました。各メーカーの特徴を確認しつつ、曇りでも発電する太陽光パネル(曇りの日でも発電量が低下しづらい太陽光パネル)を探っていきましょう。
Qセルズ
Qセルズは、ドイツ・ライプチヒで研究開発を行う太陽光発電システムです。太陽電池モジュールメーカーのパイオニアとして低照度に強い太陽光発電システムの開発に注力し、2012年から日本国内で住宅用太陽光発電システムの販売を開始しています。
2014年の実発電量テストにおいて、2年連続「最優秀多結晶モジュール」を獲得しており、国内外のメーカーのモジュールと比較しても年間の発電量は最多を誇るなど、天候に関わらず発電効率が良いと評判です。発電効率が高い理由として、特に以下のことが挙げられています。
- 低照度発電性能
- 独自の最先端技術
北海道よりも北に位置するドイツ・ライプチで、わずかな太陽光を最大限に活かした低照度発電性能を研究開発しているため、曇天時でも高いパフォーマンスが期待できます。
また、太陽光をより効率よく取り込める仕組み(特殊なナノ・コーティング技術)を使用するなど、Qセルズ独自の最先端技術を使って発電効率を高めています。

マキシオン
マキシオンのソーラーパネルは独自設計のセルを使用することで、曇りの日でも従来のパネルより多くのエネルギーを生み出しています。
赤と青の波長を含むより広範囲の太陽光を捕らえる仕組みを採用し、曇りの日や木や電柱等で影になりやすい環境でも効率的に電気エネルギーに変換する構造が特徴。住宅用太陽光パネルの主力製品は、以下の2種類。
- マキシオンソーラーパネル
- パフォーマンス太陽光パネル
耐久性、信頼性、変換効率、コストパフォーマンスの良さが魅力のマキシオンソーラーパネル。短冊状セルからなる最先端テクノロジーによりパネル出⼒を最⼤化することに成功しています。
さらに並列回路設計を取り入れ、従来のパネルより多くの発電量の確保できるよう設計。曇天時の発電効率に寄与しているパネルと言えるでしょう。
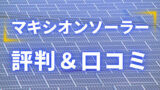
パナソニック
パナソニック製太陽光パネルの代表機種といえばHITシリーズが有名です。パナソニック社は三洋電機を買収し技術開発に力を入れてきました。HITシリーズのエネルギー変換効率は業界トップ水準となっており、実際、狭い屋根でも発電量が多く、曇りや雪の日でも十分な発電量を保つパネルとして定評があります。
HITパネルの発電効率化を上げているのが、以下の2つの素材です。発電ロスを最小限に抑えることに寄与しています。
- アモルファスシリコン
- 低反射ガラス
「アモルファス」というフィルムを採用し、僅かな光でも電気エネルギーに変換。曇りの日や朝夕時など日当たりが弱いときにもしっかり発電できるという特徴があります。
さらにアモルファスシリコンと単結晶を掛け合わせることで、従来型の太陽光発電の特徴でもある「温度が上がると発電効率が低下する」という弱点も克服しています。
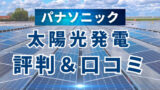
長州産業
長州産業の太陽光パネルで変換効率が優れているシリーズといえば「プレミアムブルー」が有名です。業界トップクラスの実効変換効率を実現している太陽光パネルといわれており、屋根のスペースに合わせて、3つのタイプ(公称最大出力333W・300W・275W)が販売されています。
プレミアムブルーのパネルには、曇天時でも変換効率を上げるために、主に以下のような技術を採用しています。
- ヘテロ接合構造セル
- 波長変換
- 白色封止材
- 電子バスバー
など
ヘテロ接合構造セルの特徴は、層の間に「真性層」と呼ばれる層を設けることで、電荷の消失を低減し発電ロスを抑えます。さらに紫外線を可視光に変換して活用する独自技術(=波長変換技術)によって、波長の短い紫外線をカットせず、可視光に変換することで出力を改善。
さらにセル裏側の封止材色を「透明→白色」に変更したことで太陽光がセルに届きやすくし、モジュールの電力損失を軽減するためにバスバーの数を「5本→9本」に増加。電子の移動距離を短くすることで、電力損失を軽減しています。

一般的な太陽光発電は曇りのとき発電しない?

太陽光発電システムの導入に際し「年間発電量」を重視することは大切ですが、そもそも悪天候でも発電するのでしょうか?
天候に左右されないパネルや曇りに強いソーラーパネルを探す前に、まずは曇りの日でも太陽光システムは発電するのか確認していきましょう。
曇りでも発電は可能
太陽放射は雲をすり抜けるため、曇りの日でも発電します。
気象庁(2022年)の天候データを参考にすると、日本海側・太平洋側など地域によって影響に違いはあるものの、以下の時期の太陽光は雲に遮られるため、発電量は減少傾向にあります。
- 梅雨シーズン(6月上旬~7月中旬)
- 台風シーズン(9月上旬~10月上旬)
とはいえ、曇りの日が続くシーズンであっても皮膚が日焼けするように、太陽の光は想像以上に強力です。発電量は日射量に左右されるため天候の影響を大きく受けますが、太陽光が少しでもあたれば太陽光発電システムは発電する(=発電量はゼロではない)と覚えておきましょう。
では具体的に、晴れの日と曇りの日では発電量にどのくらいの違いがあるのでしょうか?
曇天時の発電量の変化
発電量は、入射する光エネルギー量に比例します。曇天時でも発電しないわけではありませんが、当然晴天時と比較すると雲天時のエネルギー出力は低下します。
以下は一般的な太陽光発電システムである「シリコン系太陽発電池」を使用した場合の晴天時と、曇天時の発電量を示したものです。
| 項目 | 晴天時 | 曇天時 |
|---|---|---|
| 発電量 | 100% | 40~60% |
曇天時では、晴天時と比べると明らかに発電量は減少しますが、それでも晴天時の半分程度あることが分かります。
発電量は各メーカーの性能レベルによっても違ってきますので、曇りや雨だからと一喜一憂せず、「1日ごとの発電量」で判断することが大切です。
各メーカーの雨天時の発電量
太陽光発電の雨天時の発電量は、晴天時の5~20%程度しか発電しません。
曇天時・雨天時の発電量について、各メーカーの公式サイトではどのように報告されているのか、以下の表を見てみましょう。
| メーカー名 | 曇天時 | 雨天時 |
|---|---|---|
| パナソニック | 晴天の1/3~1/10 | 晴天の1/5~1/20 |
| エクソル | 晴天の1/3~1/10 | 晴天の1/5~1/20 |
| 長州産業 | 晴天の1割~5割 | |
| Qセルズ | 晴れの1/5の照度で97%~98% | |
| マキシオン | 公式発表なし | |
| シャープ | 公式発表なし | |
| 京セラ | 公式発表なし | |
| カナディアン・ソーラー | 公式発表なし | |
上記のとおり、晴天時の発電量と比べると雨天時は激減することが分かりますが、発電量は日射量に比例するので、具体的な数字として公式発表されていないメーカーも多くあります。
しかし、近年では多くのメーカーが発電効率の良いソーラーパネルを実現させるべく、切磋琢磨しています。ただ、昔に比べて性能レベルは確実にアップしているものの、太陽光パネルの設置枚数によっても発電量は変化しますし、ソーラーパネルの品質によっても変換効率の良し悪しは異なります。
ですから、天候に左右されない(曇りの日でも発電量が減少しにくい)太陽光パネルを探し当てることが大切です。

曇りでも発電する太陽光パネルを検討しよう

太陽光パネルは、曇天時であっても晴天時の半分ほどは発電しますから、わずかな太陽光も無駄にしないような発電効率の良い太陽光パネルを探し当てることが大切です。
メーカーそれぞれに個性や特徴があるように、パネルの大きさや性能も様々です。まずはネット上の一括見積りサイトなどを活用し、自分の家に適した太陽光パネルを調べてみるのもおすすめの方法でしょう。